表紙
|
全20巻 4500首以上の歌からなる日本最古の歌集 7世紀は柿本人麻呂、8世紀は大伴家持が手を加え長期にわたって纏められたが過程は詳しく解らず主にどのような人物が携わったかも不明。 奈良時代に完成された。 |
|||
|
雑歌(ざっか)
|
公の性質を持った宮廷関係の歌、旅で詠んだ歌、自然や四季をめでた歌など | ||
|
相聞歌(そうもんか)
|
主として男女の恋を詠みあう歌 | ||
|
挽歌(ばんか)
|
死者を悼み、哀傷する歌 | ||
|
譬喩歌(ひゆか)
|
心情を表に出さず、隠喩(いんゆ)的に詠んだ歌(多くは恋愛感情を詠まれた) | ||
|
羇旅歌(きりよか)
|
羇旅=旅の事 旅の感想をうたった歌 |
||
|
寄物陳思(きぶつちんし)
|
恋の感情を自然のものに例えた歌 | ||
|
正述心緒
(せいじゅつしんしょ) |
感情を直接詠った歌 | ||
|
詠物歌(えいぶつか)
|
季節の風物を詠んだ歌 | ||
|
東歌(あずまうた)
|
上代、東国地方で作られた民謡風の短歌 | ||
| 第1期 | 舒明天皇即位(629年)〜 壬申の乱(672年)まで | 皇室の行事や出来事に密着した歌が主流 | |
| 額田王・舒明天皇・天智天皇・有間皇子・鏡王女・藤原鎌足 | |||
| 第2期 | 平城遷都(710年)まで | 官人達の儀礼的な場での宮廷賛歌や旅の歌などがある | |
| 柿本人麻呂・高市黒人・長意貴麻呂・天武天皇・持統天皇・大津皇子・大伯皇女・志貴皇子 | |||
| 第3期 | 733年(天平5)まで | 個性的な歌が主流 | |
| 山部赤人・大伴旅人・山上憶良・高橋虫麻呂・坂上郎女 | |||
| 第4期 | 759年(天平宝字3)まで | ||
| 大伴家持・笠郎女・・大伴坂上郎女・橘諸兄・中臣宅守・狭野弟上娘子・湯原王 | |||
|
舎人(とねり)
|
天皇・皇族の身辺で御用を勤めた者。 律令制で、皇族や貴族に仕え、護衛・雑用に従事した下級官人。 内舎人(うどねり)・大舎人・東宮舎人・中宮舎人などがあり、貴族・下級官人の子弟などから選任した。 |
|
|
采女(うぬめ)
|
宮中の女官の一。天皇・皇后の側近に仕え、日常の雑事に従った者。律令制以前からあったとみられるが、律令制では諸国の郡司一族の子女のうちから容姿端麗な者を出仕させて、宮内省采女司(うねめのつかさ)が管理した。 江戸時代まで続く |
|
|
妃(ひ)
|
皇族出身の妻 | |
|
夫人(ぶにん)
|
中央豪族出身の妻 | |
|
嬪(ひん)
|
地方豪族出身の妻 |
| 645年 |
公地公民の法
(こうちこうみんのほう) |
律令制のもとに行われた,土地や人民を公のものとした制度 |
||
| 皇室や豪族が全国に私有していた土地や人民を中央政府(朝廷)が支配し私有地や私有民は禁止され代わりに 租税をおさめる義務を負わされた。 (治水工事・道路工事・建築工事・国の仕事) 私有地が晴れて合法となるのは西暦1873年、明治政府の地租改正まで |
||||
| 645年 |
班田収授の法
(はんでんしゅうじゅ) |
農地(田)の支給・収容に関する制度 | ||
| 戸籍・計帳に基づいて、政府から受田資格を得た貴族や人民へ田が等しく班給され、死亡者の田は政府へ収公された。 こうして班給された田は課税対象であり、その収穫から租が徴収された。 |
||||
| 645年 |
祖・庸・調の税制の定
(そようちょうのぜいせいのさだめ) |
人民が国に税をおさめる方法 | ||
| 祖=稲の収穫の一部 庸=労働あるいは布織物 調=地方の特産物 |
||||
| 658年 |
有間皇子の変
|
父である孝徳天皇が中大兄皇子と対立して孤立し、失意のうちに難波で没したあと、 有力な皇位後継者として注目された有間皇子を皇太子であった中大兄皇子に疎んでいた。 有間皇子は難を逃れるため、自分には皇位を継承する器がないことを知らしめるため、狂人を装っていたといわれる。 天皇家が療養に紀伊国牟婁温湯に行くと留守官として蘇我赤兄が都に残った。 その時赤兄にそそのかされて謀反を起こそうとしていたところ赤兄に邸宅を取り囲まれ捕らえられ処刑された。 |
664年 |
甲子の改革令
|
冠位十二階を改訂し、大化の改新で大化3年(647年)制定(施行は648年にされた)、冠位十三階で新たにもうけた |
| 670年 |
庚午年籍
(かのえうまねんじゃく) |
庚午(こうご)とも言われ日本最初の全国的戸籍=中央集権 | ||
| 籍が作成された跡をたどると,畿内とその周辺はいうまでもなく、東は上野国・常陸国,西は九州諸国に及び、 まさに全国規模で実施されたことを示している(続日本紀、新撰姓氏録) | ||||
| 671年 |
政府最高首脳人事
|
太政大臣(だじょうだいじん) | 大友皇子 | |
| 五大官 | 左大臣(さだいじん) | 蘇我臣赤兄(そがのおみあかえ) | ||
| 右大臣(うだいじん) | 中臣蓮金(なかとみのむらじこがね) | |||
| 御史大夫(ぎょしたいふ) | 蘇我臣果安(そがのおみはたやす) 臣勢臣人(このせのおみひと) 紀臣大人(きのおみうし) |
|||
| 臣(うじ)蓮(むらじ)は身分を表す姓(かばね) | ||||
| 671年 |
漏刻台
(ろうこくだい) |
琵琶湖岸の新しい内裏の一角で、漏刻(水時計)を使って初めて鐘鼓を打って時を知らせる | ||
| 672年 |
禊の儀式
(みそぎのぎしき) |
禊式は清らかな水で身体を浄めあらゆる汚れを払って神に平伏す儀式 |
| 位置については様々に考えられ朝明川であるとかいう説もあるそうです | ||
| 『日本書紀』には天武天皇は『旦於朝明郡迹太川辺望拝天照大神』とありまたその原資料として採用したと思われる「安斗智徳日記」では、「辰時、於明朝郡迹大川上、而拝礼天照大神拝礼。」とあるようです。 迹大川(とほがわ)のほぼ真南に天照大御神の社、伊勢神宮があったとして、迹大川から祈りを捧げたということだと言う説があります。 天照大御神は皇室の祖神・太陽の女神とされる |
||
| 673年 |
大嘗祭
|
(おおにえのまつり/だいじょうさい)という 天皇が即位後始めて行う新嘗祭(にいなめさい)のことでその年の実りの穀物を天照大御神と天の神、地の神に捧げる特別厳粛、盛大に行う |
| 天武天皇の時代に始めて確立され、天武天皇崩御後は生前譲位→新帝の大嘗祭→先帝崩御→火葬→埋葬(先帝崩御→新帝即位→先帝の火葬→埋葬→新帝の大嘗祭)という一定の流れが確立される 火葬は持統天皇から |
||
| 681年 |
律令制の制
|
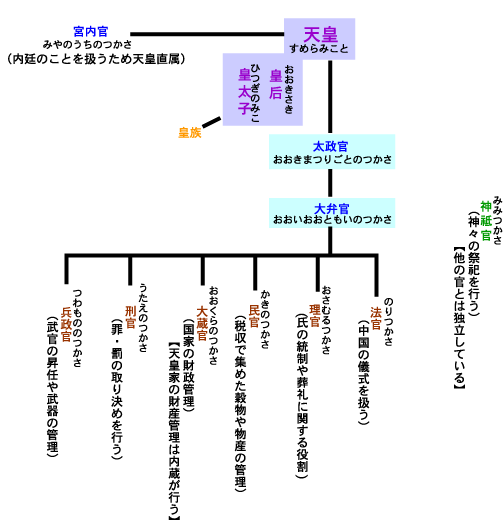 |
| 斎宮(さいぐう/いつきのみや) | 皇大神を祭る宮(=伊勢神宮) | |
|
斎(いつき)
|
潔斎(けっさい)して神に仕えること | |
|
潔斎(けっさい)
|
神事などの前に、酒や肉食などをつつしみ、沐浴(もくよく)をするなどして心身をきよめること | |
|
斎王(さいおう)
斎皇女(いつきのみこ) |
齋を行う者 | |
| 未婚の内親王(天皇の姉妹、嫡出の皇女または嫡男系嫡出の皇孫たる女子)から選ばれる | ||
| 1〜3年の潔斎の後、伊勢の斎宮へ群行(斎王が都から伊勢まで行くこと、任を終えて伊勢から都へ帰ること)することになります。 そこで斎王は天皇の在位間、陛下と大和國安寧を祈り伊勢神宮に仕える。 陛下の崩御、自身の病、肉親の不幸など悲しみの時が迎えくるまで京に帰ることはできない。 |
||
| ・流れ・ | ||
| 年 |
事柄
|
|
| 卜定にて人選、勅使が知らせる | 卜定(ぼくじょう)は占いによって吉凶を定めること | |
| 卜部が皇女邸で清め式を施行する | 律令制で、神祇官(じんぎかん/みみつかさ)に仕えた職員 | |
| 邸の四方が清められた木綿で囲まれる [選ばれた事を知らせる印にもなる] | ||
| 1 | ||
| 大祓をし鴨川で禊を行い、 初齋院に入いる | 宮内に設けられた初齋院で身を清める(=1年間) | |
| 2 | ||
| 再度、大祓をし鴨川で禊を行う | これが済むと野宮(ののみや)へ入る(=1年間) | |
| 野宮=皇女や女王が斎宮・斎院になるとき、潔斎のため一年間こもった仮の宮殿 斎宮のものは嵯峨、斎院のものは紫野に設けた |
||
| 3 | ||
| 伊勢へ入る | 禊を行う | |
| 天皇から発遣の儀式が行われる | ||
| 伊勢の斎宮へ群行 | ||